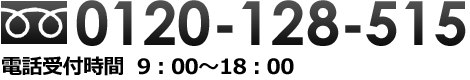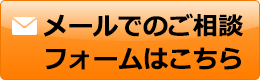弊社が所在地を構えている埼玉県行田市は、江戸時代から足袋(たび)作りが盛んな場所として知られています。
今回は、行田市でなぜ足袋が作られ、どのように発展してきたのか、また足袋に関連する施設などをご紹介しながら、地域の魅力をお伝えします。
そもそも行田市ってどんなところ?
まず、行田の足袋について触れる前に、行田市について簡単にご説明します。行田市には、関東七名城の一つである忍城(おしじょう)があり、戦国時代には重要な拠点のひとつでした。この忍城を中心に城下町が形成され、歴史と伝統が今も大切に守られています。
なぜ行田市で足袋がつくられたのか
足袋の製造が始まった時期については、貞享年間(1684~1688年)に足袋製造が始まったという伝承や、享保年間(1716~1735年)の絵図に足袋屋が描いてあることから、江戸時代からとされています。
この行田の地で足袋が作られるようになった理由は大きくふたつあげられます。
➀土壌が、綿花(めんか)の栽培に適していた
➁気候が藍染め(あいぞめ)に非常に適していた
利根川や荒川の豊かな水と肥沃な土壌が育んだ綿花栽培と、藍染めに適した気候から、足袋の材料を揃えやすいという条件が揃っていたということです。
行田足袋の評判とは
行田で作られた足袋は、特に品質が良く、江戸時代の商人や武士にも人気があったそうです。町が発展するにつれて、足袋の需要も増え、行田は足袋作りの中心地として栄えていきました。
現在では、日本遺産にも「和装文化の足元を支え続ける足袋蔵のまち行田」として認定されています。
足袋にまつわる施設の紹介
行田市には、足袋に関連するいくつかの施設があり、観光客や地元の人々にとって、足袋の魅力を再発見する場所となっています。以下に代表的な施設を紹介します。
➀足袋とくらしの博物館
もともと「牧野本店」というお店の足袋工場を活用して博物館となっていて、My足袋作り体験では、用意されている生地から選ぶだけでなく持ち込みの生地でも足袋作りが可能だそうです!
所在地 :埼玉県行田市行田1-2
営業時間:10:00〜15:00/土曜・日曜(夏期休暇あり。冬期は12月半ば〜1月上旬まで休館)
http://www.tabigura.net/tabihaku.html
➁きねや足袋株式会社
様々な種類の足袋を販売していますが、「足袋の館」では足袋を制作する様子が見学できます。
所在地 :埼玉県行田市佐間1-28-49
営業時間:8:30~11:45・13:00~17:00/平日
③ぶらっと♪ぎょうだ
行田にちなんだ名産品などが揃っている観光物産館です。ここでもさまざまなデザインの足袋が買えます。
所在地 :行田市忍2丁目1番8号(行田市商工センター1階)
営業時間:9:30~17:00
https://www.gyoda-kankoukyoukai.jp/shopping/998
④手打ちそば 忠次郎蔵
足袋の原料問屋として使われていた「旧忠次郎商店」の蔵造り店舗(店蔵)を改装した日本蕎麦の店です。
所在地 :行田市忍1-4-6
営業時間:11:00〜14:00/火曜~日曜
今回ご紹介したもの以外にも足袋蔵や営業を続ける足袋屋があり、忍城の中にある資料展示では、行田足袋の制作に使われた機械や当時の様子を見ることができます。
行田市の足袋文化を通じて
行田市は、足袋作りの伝統が色濃く残る町で、地域の文化を深く感じることができる場所です。足袋の歴史や作り手の技術を学ぶことで、行田市の魅力をさらに実感することができるのではないでしょうか。
行田市を訪れた際には、ぜひ足袋文化が残る下町文化に触れてみてください!