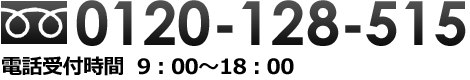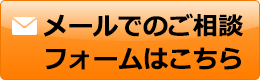takaです。先月、株価にもAIの未来図にもDeepSeek(ディープシーク)は、大きな衝撃をもたらしました。
その後、ディープシークについては、賛否が交錯している状況です。
ディープシークは正解率が低い?
アメリカの情報サイト格付け機関「ニュースガード」は、ディープシークの回答は正答率が17%だったとの検証結果を発表しました。
ニュースなどに関する質問に対し、誤った主張が30%、曖昧か役に立たない主張が53%で計83%に上ったといいます。
オープンAIの技術を不正利用?
ディープシークが短期間で開発され、開発費も破格に低い理由として、ディープシークのモデルがオープンAIの技術を不正利用している疑惑も浮上しています。ディープシークは、オープンAIのAPIから大量のデータを取得し、モデルの学習に利用した可能性が指摘されているようです。
中国発の「ディープシーク」は安全なのか?
ディープシークはプライバシーポリシーで、収集する情報を「顧客が提供する情報」「自動的に収集する情報」として明示しています。
これらのデータは「中国本土にある安全なサーバーで保管する」と説明していますが、中国共産党の配下にある可能性は否定できません。
AIの専門家からは、ウェブやアプリのインターフェースをもつ、誰でも利用できるAIモデルでは、ディープシークに限らず、AIに向けて発せられた指示や質問は、答えも含め、メーカー側が利用できるようになっている」と言っています。
アメリカも信用しない方が良いと思いますが、中国共産党が支援するAIモデルが世界の国家安全保障を脅かす可能性は否定できません。
日本初の生成AIが開発されると良いのですが・・・
ディープシークの利用制限
中国共産党が支援するAIモデルが自国の国家安全保障を脅かすという懸念から、一部の国では、ディープシークの利用制限が始まっています。
イタリア情報保護当局は、1/30日、ディープシークが適切に情報処理しているか調査を始めると発表しました。
イタリア国内でのデータ処理を即座に制限するようディープシークに命じました。
アイルランド当局もデータ処理に関する情報提供を書面で要請し、フランスも同様の対応を取るようです。
台湾は、1/30日、公的機関や重要インフラ機関を対象にディープシークの利用を制限すると発表しました。
ディープシークの登場は、技術革新をもたらす一方で、国家安全保障や知的財産保護といった重要な課題を表面化させました。
ディープシークの急速な普及
ディープシークについては、安全性や安全保障の問題で、各国の規制がかかる一方で
ディープシークを導入した企業が200社を超えるという集計結果も出ています。
アメリカのマイクロソフト、NVIDIA、アマゾンのような巨大企業が、ディープシークを導入し、
中国でもファーウェイ、テンセント、百度、アリババなど中国クラウド業者がディープシークの利用を始めています。
賛否が交錯するディープシークですが、暫くは真偽を見守る必要がありそうです。
みなさんは、どう考えますか?